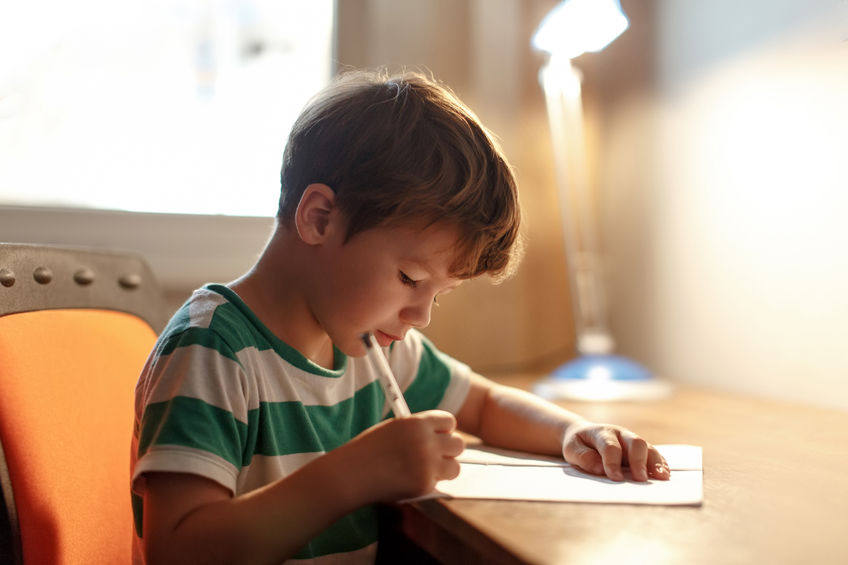共働き家庭も増え、今と昔ではライフスタイルにも変化が現れています。
その中で、子どもたちの家庭での過ごし方も大きく変わってきています。
家庭で過ごす時間が以前より減りつつある中で、家庭内で子どもたちの勉強時間をどう確保するか、またどう勉強を見てあげるのか、悩んでいる家庭も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな共働き家庭で子どもの勉強をみてあげるためのポイントを低学年・高学年にわけてご紹介していきます。
目次
小学校低学年の帰宅後スケジュール

同じ共働きの家庭でも、帰宅時間が何時になるかで多少違ってくるかと思います。
帰宅後のスケジュールを考える時はまずは絶対に守る時間を決め、そこから逆算をしていきましょう。
例えば、小学校低学年であれば、21時頃には寝かせたいと考えているご家庭も多いのではないでしょうか。
そうするとこの21時というのが絶対に守る時間になります。帰宅するのが18時30分だとするならば、就寝までの2時間30分の内に夕飯を食べ、お風呂に入り、次の日の準備をして、勉強をするので、やることはたくさんあります。
では、実際にどのようなスケジュールがよいのでしょうか。あくまでも参考にしていただけるとよいかと思います。
18時30分:帰宅、明日の準備
18時30分に帰宅をしたら、まずは明日の準備等をさせます。自分で時間割を見て、教科書などを準備させます。
帰宅後すぐに明日の準備をさせるのは、明日急きょ必要なものがないか、確認させるためです。
子どもは寝る前や朝学校に行く前になって、「○○が必要だった!」などと言うことが多々あります。
すぐに準備できるものであればいいのですが、すぐに準備できなかったり、探さなければいけないものもあったりします。
親もいきなり言われると「なんで今言うの?」となってしまうので、そうならないようにまず明日の準備をさせましょう。
終わったら、子どもは自由時間でも構いません。子どもが遊んでいてくれれば、その間親も軽く片づけしたり、夕飯の準備をすることができます。
19時:夕飯、お風呂
19時頃には夕飯を食べ、お風呂に入ります。一緒にご飯を食べることも、食事のマナーを教えたり、貴重な会話時間になります。お風呂も同じです。
低学年だと親と一緒にお風呂に入る家庭もまだ多いかと思います。
一緒にいられる大切な時間ですので、ゆっくり話をしたり、簡単な問題を出してちょっとした勉強の時間を確保するのもよいかと思います。
20時:勉強、就寝準備
20時から勉強スタートです。とはいえ、小学校低学年の場合、集中力はあまり続きませんので、30分~45分くらいで十分かと思います。
無理にダラダラとやっても意味がないの、小学校の1コマの授業時間である45分できたらよいぐらいにおもっていてよいのではないでしょうか。
ただ45分というと、実際のところ時間としてはあっという間です。
まずは優先して宿題を確認しましょう。この時点で、学童保育などに放課後いっていた場合はすでに終わっている場合が多いかと思います。
なので、学童保育で終わらせた宿題をチェックします。学童保育では、宿題をやらせる時間はあっても、あくまでもやらせるだけで、つきっきりで見てもらえるわけではないので、適当にやっていたり、間違いが多いことも。
ですので、分からなかったり、間違った箇所を一緒にやったり、丁寧に直させたりします。
また、低学年の宿題で多いのが音読です。
これも親と面と向かってやるしかないので、優先して行います。
だいたい宿題が終わったら、時間もある程度経ちますし、子どもの集中力もなくなってしまうと思うので、平日の勉強はこれで十分だと考えます。
中には、塾に通っているお友達がいて、その子は学校の勉強のもっと先まで出来ている、どんどん差が開いてしまう、と焦ってしまう親も多いのかもしれませんが、焦る必要はありません。
例え先のことを勉強していたとしても、いずれその勉強は学校でやることになります。
その時にできるようになれば問題ありません。
低学年はまずひらがなの“とめ”や“はね”などしっかりできたり、計算力を身に付けたり基礎基本をしっかりと身に付けることが大切です。
21時:就寝
21時には就寝し、朝の6時に起床するならば、9時間の睡眠時間を確保することができます。
低学年のうちは8時間から10時間の睡眠が必要と言われています。
もし、勉強時間を伸ばして、睡眠不足になってしまうと、学校での授業に影響が出てしまいます。
それでは家庭学習の意味が無くなってしまいますので、あまり無理させ過ぎず、家庭での学習時間を確保しましょう。
小学校低学年のうちは、勉強する習慣を身に付けさせることを意識しましょう。
自分の勉強スタイルが出来てくると、高学年以降の勉強も自主的に出来るようになっていきます。
小学校高学年の帰宅後スケジュール

小学校高学年になると、学童保育には行かず、親が帰宅するまで自宅で待っている子も多くなってきます。
そのような場合、先ほどまでのスケジュールと変わってくる場面も出てきます。
16時:帰宅、宿題、自由時間
学校や学校までの距離にもよって多少前後するかと思いますが、16時頃までには帰宅します。
親が帰ってくるのが18時30分とすると、2時間30分もあります。
最近ではこの時間に塾や習い事する子も多くなっています。
もし、塾や習い事に行かないならば、まずは宿題だけ確実に終わらせておくようにさせます。
高学年になればゲームをしたり、動画をみたり、様々な誘惑もあるかと思いますが、宿題をきちんとやれば、こういった楽しみを与えてもよいのではないでしょうか。
もちろん、最初から上手く宿題を終わらせておくことが出来なかったり、逆に慣れてくると、ゲームで遊び過ぎて終わっていなかったり、上手くはいかないかもしれません。
仕事が終わり、疲れて帰宅したら、子どもが宿題やっていなかったら、つい大きな声を出したくなってしまいますが、「どうしたらできるようになるか」を一緒に考えてあげることが大切です。
宿題がいつも同じようなものなら、細かく何時から何時までにはこれをやる、とフロー表を作ってあげたり、子どもに帰宅したメールをさせるような家庭ならば、その時に宿題も連絡させて、具体的に指示を出したり、最初は大変かと思いますが、慣れてくれば子ども自身で上手くできるようになっていきます。
誘惑に負けず、やることをやる能力を身に付けさせること、自分でスケジュール管理することは、中学、高校、そして社会人になっても大切なことですので、根気強く向き合いましょう。
18時30分:以降は小学校低学年と同じスケジュール
親の帰宅後は、小学校低学年のスケジュールと同じでよいかと思います。
つまり、19時~20時までに夕食とお風呂を済ませ、20時頃からまた勉強を再開させます。
まずは夕方にやった宿題などで分からなかったところを一緒にやります。
学校から宿題が出るのは、学習の定着を図るためです。
分からないところをそのままにしておくことがないように、親も軽く宿題に目を通してあげましょう。
小学校高学年になると親と一緒にやる宿題は少ないと思いますので、この時間は自主学習のようなものをさせるのもよいかと思います。
学校外の教材を取り入れてもいいですし、本を読むでもよいかと思います。高学年になると就寝時間も遅くなってきますが、22時には就寝できるようにさせましょう。
小学校高学年では、自ら学習する力、意欲的に取り組む姿勢を身に付けさせましょう。
また、自分の能力を理解し、スケジュール管理が自分できるようになっていくこともその後大切な力です。
親は自立を促しつつ、適度な声掛けでサポートしていきましょう。
休日の過ごし方も工夫次第で学べることがたくさん!

平日に学校の宿題で手がいっぱいで、他の勉強にまでは手が回らないという家庭でも、親の休みが土日の場合、休日に一緒に勉強するのもよいでしょう。
また、なにも座って勉強することだけが勉強ではありません。
自然の中で虫や植物の観察をしたり、動物園や水族館、科学館、美術館などで学べることもたくさんあります。
平日はなかなか体を動かす機会がないならば、一緒に体を動かすのもよいでしょう。
親が一緒にやる、子どもに親の姿を見せることで、子どもへの刺激にもなります。
大切なのは「量」より「質」
「共働き世帯」というと、あまり子どもに目が向いていないと思われてしまうことも筆者自身の経験でありますし、そのような目で見られてしまった経験のあるご家庭もあるのではないでしょうか。
でも、実際は子どもと関わる時間が少ないからこそ、その時間を大切にしたいと考えている共働き世帯も多いとはずです。
実際に、学童保育などの様子も見せていただいたことがありますが、子どもの勉強する教材を手作りされているご家庭も多く、それを次の日には丸付けした状態、間違ったところにはどうすれば解けるかのヒントを添えて勉強の面でやり取りをしているご家庭もあり、とても感心したこともあります。
もちろん子どもと長い時間を一緒に過ごすこともよいですが、大切なのは「質」ではないかと思います。
「質」を向上させる工夫はいくらでもできるか思うので、共働きであることに負い目を感じず、短い時間の中でも愛情をたくさん注いで子育てしていただきたいです。