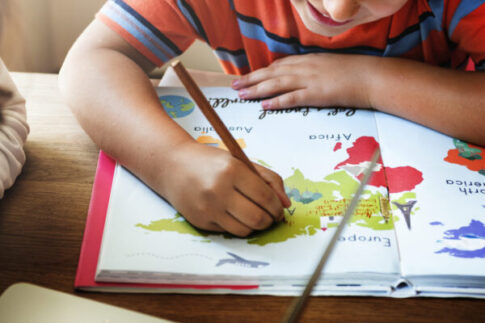勉強を続けていても、急に成績が下がったというようなケースです。
一方、成績が伸びる子もいます。
小学校高学年での成績の違いは、どのような原因から起こるのでしょうか。
目次
小学校高学年で成績が下がってしまう子の特徴
長時間の勉強は必ずしも効果的ではない
小学校高学年になると、ある程度は勉強の習慣が身につきます。
長時間の勉強にも慣れてくるでしょう。
一方で、長時間の勉強が成績に結びつかない場合もあります。その原因は、子どもが集中できていないことにあります。
勉強は、集中して行わなくてはなりません。時間をかけて勉強しても、集中できなければ効果は少ないでしょう。
そして、長時間の勉強が、かえって集中力を削いでしまうケースがあります。
どんな子どもでも、一定時間を過ぎると集中は切れます。
その時は適度に休憩し、疲れを回復させ、集中力を戻す必要があります。
しかし、休まずに長時間勉強をすると、集中力を回復するというステップがありません。
すると、集中力が下がったまま長時間勉強をすることになります。これは、成績が下がる原因となります。
勉強は、もちろん時間をかけて積み重ねる必要があります。
ただし、一度に長時間勉強をさせても、効果が少ないことも事実です。
集中力がずば抜けている子供でも、休まずに長時間勉強させることは、やはり効果的とは言えません。
高学年になると目立ってくる特有の問題点
長時間勉強が持つ危険性は、特に小学校高学年で目立ちます。
小学校高学年は、長時間の勉強に慣れています。
慣れているからこそ、「集中して勉強しよう」という感覚が薄くなり、ただ勉強を続けるだけになる場合があります。
なんとなく続けることは、集中力の低下の大きな原因です。
時間をかけている分、自分では勉強した気になります。
しかし、集中していないために成績が上がらず、下がってしまう場合もあります。
小学校高学年で成績が伸びる子の特徴

こまめに勉強時間を区切っている
小学校高学年で成績が伸びる子供は、連続して長時間勉強をしているとは限りません。
時間を区切って効率的に勉強を進めている子どもが多いです。
時間を区切ると集中力が回復します。
集中力が回復すれば、「集中して勉強しよう」という感覚も強くなります。
なんとなく勉強を続けるという感覚ではなく、一つ一つ集中して行うという感覚です。
このような習慣が積み重なることで、集中力の維持が可能になります。
ただし、あくまで休まずに長時間勉強するようなことはない、ということです。
決して勉強時間が少ないわけではありません。
一度に長時間の勉強をしないというだけで、こまめに区切った勉強時間を合計すれば、ある程度の勉強時間になります。
成績は、もちろん勉強時間に関係します。ただ、休まずに長時間勉強をしたから成績が上がるわけではありません。
こまめに区切り、集中力を回復させ、コツコツ勉強を重ねることで、成績が上がります。
こまめに区切った勉強時間が、コツコツ積み重なって成績につながる、とイメージしてみてください。
得意分野と苦手分野のバランスが良い
小学校高学年で成績が伸びる子は、得意分野と苦手分野のバランスがうまいです。
受験勉強は、苦手分野の対策だけでは足りません。
特に小学校高学年になると、自分の得意分野の演習を重ね、きちんとした得点源にする必要があります。
いくら得意分野でも、演習を重ねなければ成績は下がり、得点源にすることはできません。
苦手分野を重点的に対策しつつ、同時に得意分野の演習も行い、実力を養う必要があります。
もちろん、得意分野の演習だけでも足りません。得意分野だけで受験範囲をカバーすることは難しいです。
苦手分野もある程度克服し、実力を養うことが必要です。
このようなバランス感覚が、小学校高学年で成績が伸びる子供の大きな特徴です。
そして、このバランス感覚を養うためには、こまめに勉強時間を区切った方が効果的です。
例えば、「この時間は苦手分野を勉強し、その後は得意分野の演習をしよう」といった感覚が大切です。
そのためには、時間で区切る必要があります。
自分が何の勉強をしているかという感覚が身についている
さらに、勉強時間の間で少し休憩し、頭を休め、集中力を回復させなくてはなりません。
長時間勉強をさせるだけだと、「今自分は何の勉強をしているか」という感覚が薄くなります。
苦手分野を勉強しているのか得意分野を勉強しているのかわからなくなれば、効果的な勉強とは言えません。
一方で、成績が伸びる子は、「今自分は何の勉強をしているか」という感覚が強いです。
そして、この感覚は勉強時間を区切った方が身につきます。
時間を区切ることでメリハリが生まれ、勉強した内容がわかりやすくなるからです。
小学校高学年で成績が下がってしまった子への接し方
集中力を回復するために短時間勉強を取り入れる
小学校高学年で成績が下がってしまった子は、集中力の低下が大きな原因と言えます。
そのため、集中力の回復を第一に考えることが大切です。
子どもに集中力をつけさせるには、長時間勉強より短時間勉強が効果的です。
短時間でも「集中できた」という感覚を持たせれば、集中力は回復します。
勉強に対する達成感を与える
そして、短時間でも集中して勉強ができたら、「今自分は何を覚えたのか」という点を確認してみてください。
ここが共有できれば、子どもにとって達成感が生まれます。
小学校高学年で集中力が下がる原因の一つには、勉強に対する達成感がないことが挙げられます。
勉強に慣れてしまったために、特に達成感を持つこともなく、なんとなく勉強を続けているという状態です。
先ほども述べたように、なんとなく続けることは、集中力の低下の大きな原因です。
一方で、勉強に達成感があれば、なんとなく続けていた勉強におもしろみが生まれます。
すると、なんとなく続けるのではなく、「集中して勉強しよう」という感覚が生まれます。達成感は、集中力アップに大きく貢献するのです。
受験中に出てくる悩みがある場合は一つ一つ整理をしてあげる
なかには、受験に悩んでしまい、成績が下がってしまう子もいます。
悩みがあると、子どもはどうしても集中できません。
集中できないと、成績は下がってしまいます。
このようなケースは、悩みが原因で集中力が下がり、集中力の低下によって成績が下がるという例です。
そのため、集中力をつけさせる前に、まず子供と悩みを共有する必要があります。
例えば、「どうしても志望校に行きたいけど、成績が伸びない」「どうしてもこの単元がわからない」「悩みが重なって、どうしても勉強する気が起きない」など、いろいろな悩みが考えられます。
ただ、このような子は、悩みさえ解決すれば高い集中力を発揮します。
これだけ悩むということは、もともとは勉強に対してやる気があります。
そのため、悩みの解決を最優先する必要があります。
そうすれば、勉強に対するやる気がある分、集中力は回復しやすいです。
どうしても志望校が難しい場合は、他の学校を探してあげることも一つの方法です。
どうしてもわからない単元があれば、勉強習慣を見直すこと、あるいは最低限覚える知識だけ覚え、何とか他の単元でカバーするという方法もあります。
悩みが重なって勉強する気が起きない子に対しては、悩みを一つ一つ整理すること、もう一度進路について一緒に考えてあげることなど、とにかく子どもの状況を把握する必要があります。
他にも、子どもが悩んでしまう原因はあります。
まずはその悩みを共有することが、解決の第一歩となります。
成績が伸び悩んでいたら喝を入れる前に一度声かけを!
小学校高学年で成績が下がる子と伸びる子は、勉強時間の区切りと集中力に大きな違いがあります。
ただ長時間の勉強をさせれば良いわけではありません。
子どもが勉強しているのに成績が下がった場合、ただ勉強を続けるだけになっていないか、チェックしましょう。
こまめに勉強時間を区切り、その都度集中力を回復させ、効率的な勉強をさせることが大切です。
また、悩みによって成績が下がってしまう場合もあります。
その際には、まずお子さんと悩みを共有してください。
共有することで安心感が生まれます。
ある程度悩みが解決すれば、集中して勉強しやすくなるはずです。
そのためにも、喝を入れる前に今一度子どもの状況を把握し、声かけをしてあげてください。