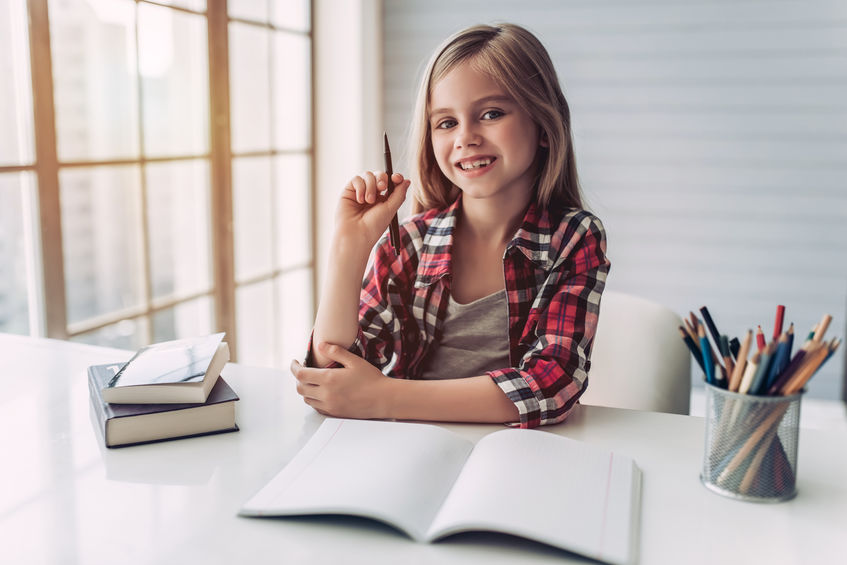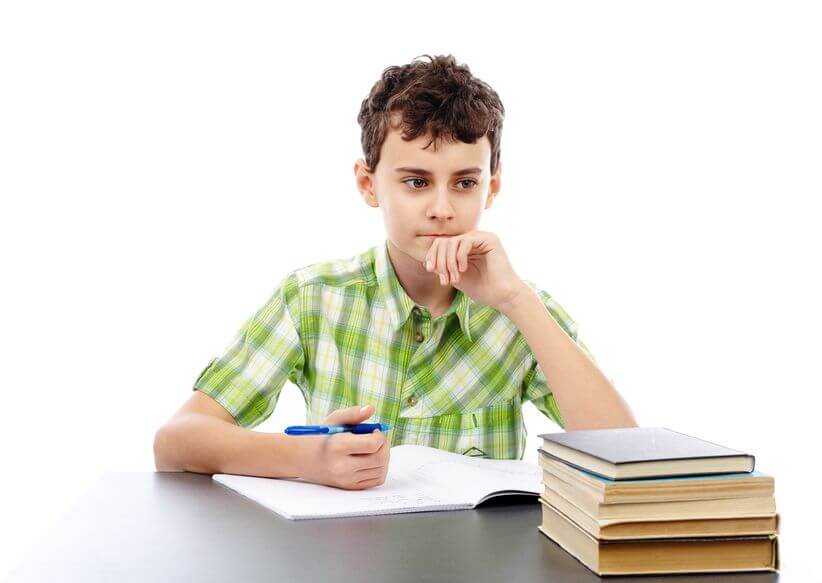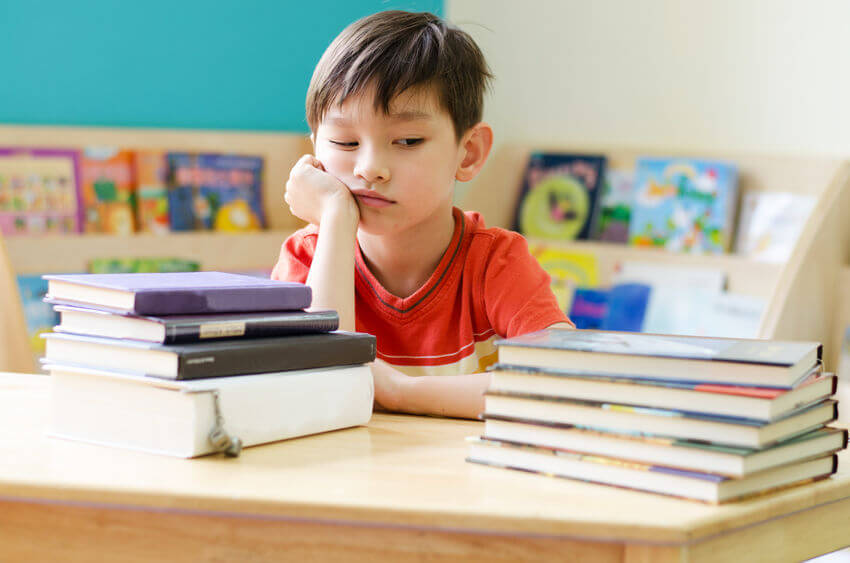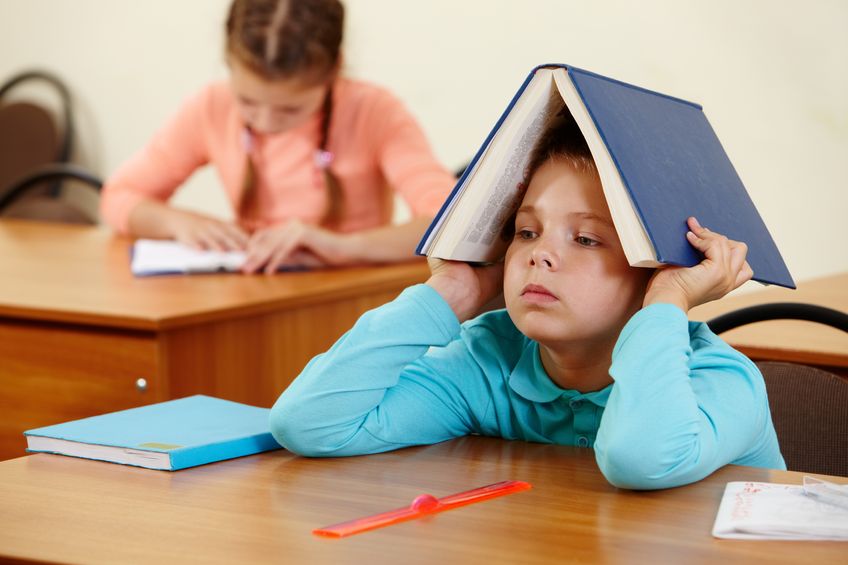どの勉強でも、必ず文章を読んだり、言葉の意味を理解したりして問題を解いていかなければなりません。
そして、国語の中にも種類があり、子ども一人ひとりが苦手とするものは違います。
その中の一つが苦手な子もいれば、複数苦手な子もいるはずです。
まずは、お子さんが国語の何が苦手なのかを把握しておきましょう。
国語の勉強の中には、「読む」「書く」「話す」「聞く」という種類があります。
小学校の教諭経験から、この四つの種類をもとに、どのように勉強をした方がいいのかを紹介していきます。
目次
「読む」ことが苦手な子どもに試して欲しいこと
小学生の中には、そもそも大人が本や新聞を読ませようとしているものに全く興味がない子がいます。
そんな子に「読むこと」を強要したり練習させたりしようとすると、
子どもはどうでもいいから読みたくない→大人が読ませようとしてくる→読むことがもっと嫌になる…
という魔のループにはまってしまいます。
そんな読み物に興味のない子には、好きなことに関するものをまず読ませるのがお勧めです。
ゲームの攻略本でも、お菓子作りの本でも、スポーツの本でも良いので、なるべく子どもが興味のあるものを読ませてください。
出来れば最初は簡単なものからが好ましいです。
そうすると、自然と文章を読み始め、書いている意味が分からないところがあれば、自分から知ろうとしていきます。
音読がオススメな理由
また、興味が無いわけではなく、能力的な問題で読むことが苦手な子もいます。
文字を映像としてしか捉えず、またその言葉の意味も分からないので、まるで暗号を見ているかのような感覚になるのです。
読むことが苦手な子に、小学校(特に低学年)でよくさせているのが、音読させるということです。
声に出すことで、自分が何を読んでいるのかを理解させることが目的です。
見ているだけでは分からないけれど、声に出して音声として耳で捉えることで、言葉の意味を理解できるという子も少なくありません。
簡単な文章から「分かる」を感じさせよう
そして、読むことが嫌だ、見たくもないという子もいます。
本→文章が多い→嫌だ(見たくもない)→挫折する
というふうになってしまうのです。
ここで大切になってくるのが、「意外と分かる」と感じさせること。
面白いものや簡単な文章をたくさん読ませて、文を読んで笑ったり、推測したりしたら、「すごい!」とすかさず褒めましょう。
読むことに対する抵抗が少なくなり、自分から読みたいという子に徐々になっていきます。
「書く」のが苦手な子どもに試して欲しいこと

「文字をきれいに書くのが苦手」「文章(作文)を書くのが苦手」の二つに分かれます。
文字を綺麗に書くコツ
文字をきれいに書くのが苦手な子には、下記のことに気を付けさせましょう。
- 文字を枠に入れること
- 止め、はね、はらいを正確に書くこと
- 文字全体のバランスを整えること
これは、子どもだけではどうにもできない問題ですので、あきらめずにしっかりと見てあげるという、大人の根気も必要です。
まずは短い文章から書く練習をしよう
文章(作文)を書くのが苦手な子は、作文となるとカチコチにフリーズしてしまいます。
そもそも作文の書き方自体がわかっていないということが多いです。
そのような子には、いきなり「長文を書きなさい」と言っても難しいので、まずは自分の中にある思い出や気持ちを短い文章で書かせてみましょう。
「運動会」「がんばった」だけでも十分です。
次は、それに言葉を少しずつ付け加えていきます。
このとき役に立つのが「イメージマップ」です。
イメージマップとは、一つの言葉を核に、どんどん言葉をリンクさせ広げていくものです。
「イメージマップ」という言葉を初めて聞いたという親御さんは、ネットなどで検索して頂くと画像が出て分かりやすいかと思います。
このイメージマップをもとに、最初に出てきた言葉にどんどん肉付けをしていくと良いでしょう。
話すのが苦手な子に試して欲しいこと
話すのが苦手な子は自分から話せないのであれば、こちらから子どもに話しかけてあげましょう。
最初は「はい、いいえ」で答えられる簡単な質問をしてあげてください。
徐々に時や場所を付け加えて答える質問にし、人や気持ちも付け加えていけるとより良いです。
「いつ、どこで、誰と、どんなことをしたか、そのときの気持ち」
ここまでを一人で言えるようになったらばっちりです。
質問を出してたくさん話を聞いてあげよう
次のステップでは、理由を言えるようにさせます。
例えば、ゲームをもらって嬉しかったときのことを説明させるとします。
- なぜ嬉しかったの?→欲しい物がもらえたから
- なぜそれが欲しかったの?→楽しそうだから
- なぜ楽しそうと思ったの?→このキャラクターが出るから
など、ちょっと子どもにとってはうっとうしいかもしれませんが、どんどん質問をしていきましょう。
子ども自身も、意外と自分が色々説明できること、理由があることに気が付いていくはずです。
そして大人は、たくさん聞いて、話して、受け入れてあげましょう。
話すことが苦ではないということを、子どもに感じさせてください。
「聞く」のが苦手な子に試して欲しいこと

読むことと同じで、子どもに聞かせるときは、興味を引くことが重要です。
読む、書くという子どもに情報を与える、つまり子どもが受け身になるときには、子どもの興味がないと始まらないのです。
好きなものや、楽しい話題をしたり、聞いていて心地の良い話し方をしたりするよう心がけましょう。
能力的に聞くことが難しい子には、視覚的要素を取り入れてあげることも有効です。
ただ話を聞かせるだけではなく、具体物や文字、絵などを取り入れ、視覚的に訴えかけます。
聞くことが難しい子は、視覚などの他の感覚で理解することも多いです。
無理やり聞かせるのではなく、その子の特徴に合った聞かせ方をするということが大切です。
大人が努力して聞く子に育てるようにしていきましょう。
国語の苦手を克服するためには語彙力を高めよう
語彙力というのは、「読む」「書く」「話す」「聞く」のすべてに関わります。
語彙を増やすためには、次の3つの方法があります。
- 本を読む(漫画、絵本、小説問わず)
- テレビを見る
- たくさん話す
本を読むことで、様々な表現の仕方を知ることができます。
テレビを見たり、たくさん話したりすることで、どういうときにどんな言葉を使うのかをしることができます。
他にもたくさん語彙を増やす方法はあると思いますが、まずできることからトライしてみてください。
どれも魔法のようにすぐにできるようになる方法はありません。
子どもと一緒に、どんな方法が合うのかを試しながら、焦らずコツコツと前進して国語の苦手を克服していきましょう。