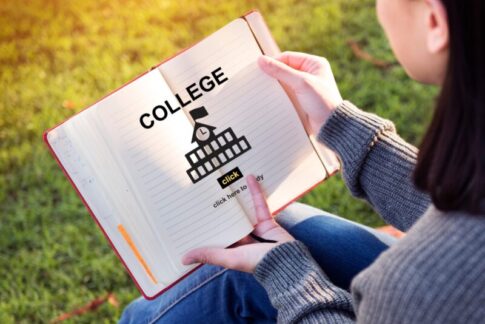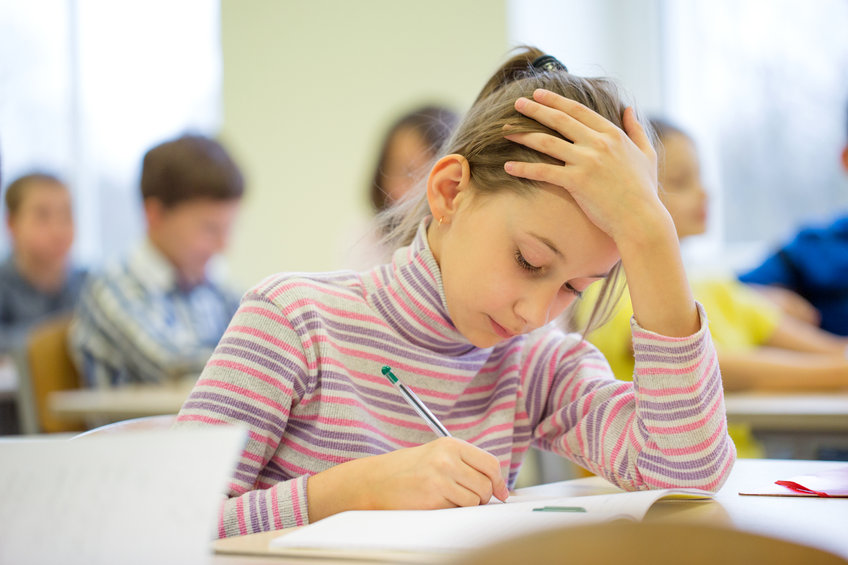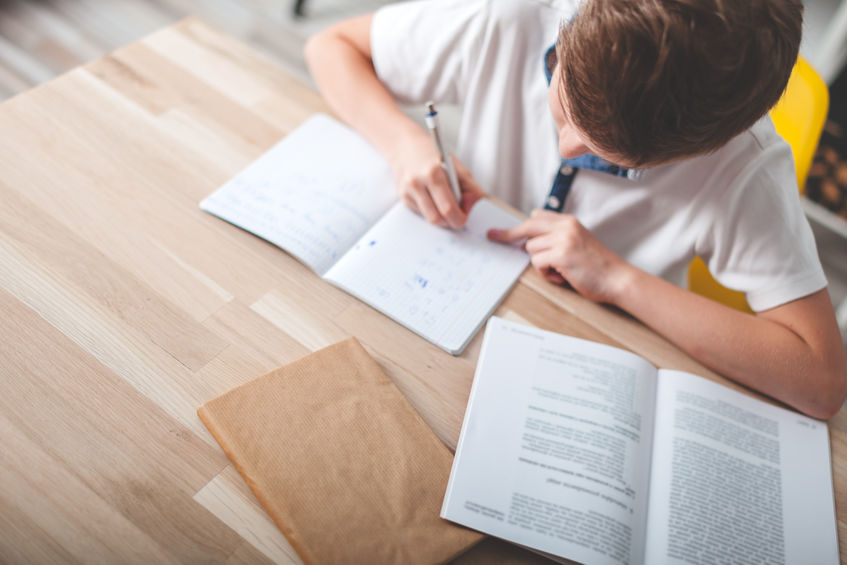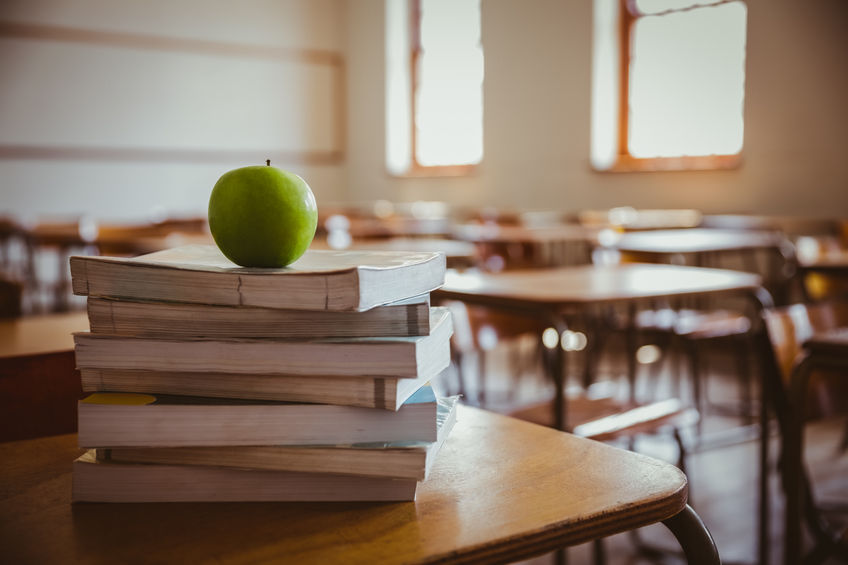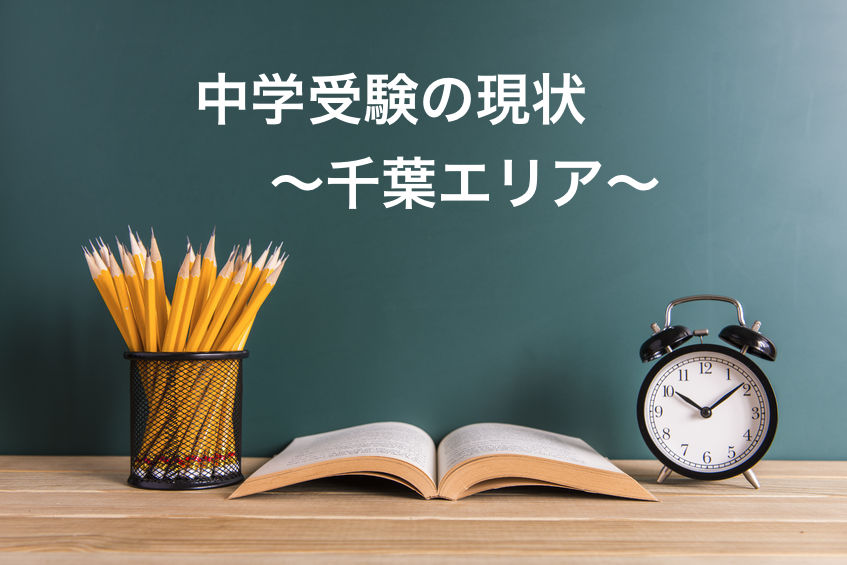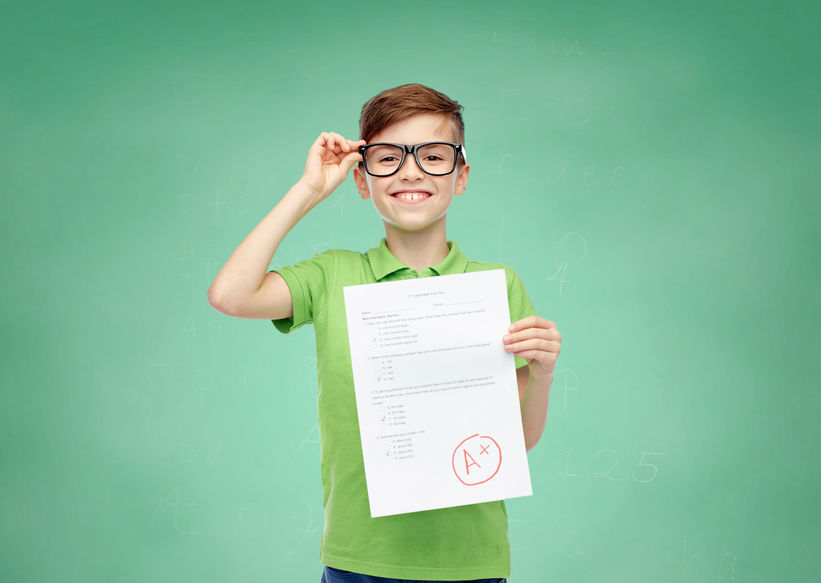近年の中学受験では中堅校への志望も多く見られ、受験をめぐる価値観も多様化しています。
難関校に入ることが全てというわけではなく、中堅校が打ち出す独自の教育方針や魅力を重要視するご家庭も少なくありません。
一方で、中堅校を目指す場合でも受験勉強はしっかり行う必要があり、傾向に沿って対策を進めることが必要不可欠です。
この記事では、塾講師の経験から中学受験で中堅校に合格するために意識すべきことについてご紹介していきます。
目次 [表示]
中堅校への志望は増えている!?
中学受験というと難関校を受験するイメージが強いですが、近年は中堅校への志望も多く見られます。
昨今、教育に対する考え方・捉え方は多様化しており、難関校に入って難関大学を目指すことが全てというわけではありません。
各ご家庭の教育方針も様々で、必ずしも難関校の大学合格・進学実績だけを重視しているわけではないのです。
こうした合格・進学実績よりも、それぞれの学校が持つ魅力、独自の教育方針などを踏まえ、多様な教育の在り方に注目しているご家庭も多いでしょう。
難関校でレベルの高い教育を受けることが普遍的な価値観というわけではなく、中堅校も含めていろいろな選択肢があることを意識してみると良いでしょう。
学校の教育方針も多様化している
難関校の場合、レベルの高い教育を通じ、難関大学の豊富な合格・進学実績に強みがありますが、中堅校は学力・学問にとどまらない独自の強みを持っている場合が多いです。
例えば国際教育に力を入れていたり、部活動や課外活動が盛んであったり、ICT教育に力を入れていたりなど、独自の教育方針・カリキュラムを打ち出す学校は多く見られます。
また、中高一貫校は面倒見の良いサポート体制も充実しており、これは中堅校も例外ではありません。
中堅校でも大学の合格・進学実績が豊富な学校も多く、こうした学校は特に受験に特化した指導体制が充実しています。
もちろんそこまで受験に特化しなくても、上記で挙げたような独自の強みのもと、面倒見の良いサポートを行う学校もたくさんあります。
このように、中堅校は独自の教育方針や校風を打ち出しやすく、それぞれで幅広い教育・指導体制を整えていることが特徴です。
中堅校の定義は?
「中堅校」という言葉に明確な定義はありませんが、一般的には最難関校・難関校ではない学校、上位校ではない学校と考えるとわかりやすいでしょう。
ただし、学校の偏差値は変動的であるほか、そもそも同じ中学校でも塾や模試によって偏差値の算出は変わります。
そのため、偏差値で一概に中堅校を定義するのは難しいですが、例えば四谷大塚の偏差値(80偏差値)でいえば50前後~60くらいまでが中堅校と言えるかもしれません。
もちろんこちらもあくまで目安であり、一概に定義できるものではありませんが、最難関校・難関校ではない学校、上位校ではない学校と考えたほうがイメージしやすいかと思います。
中堅校に合格するために徹底すべき勉強のポイント
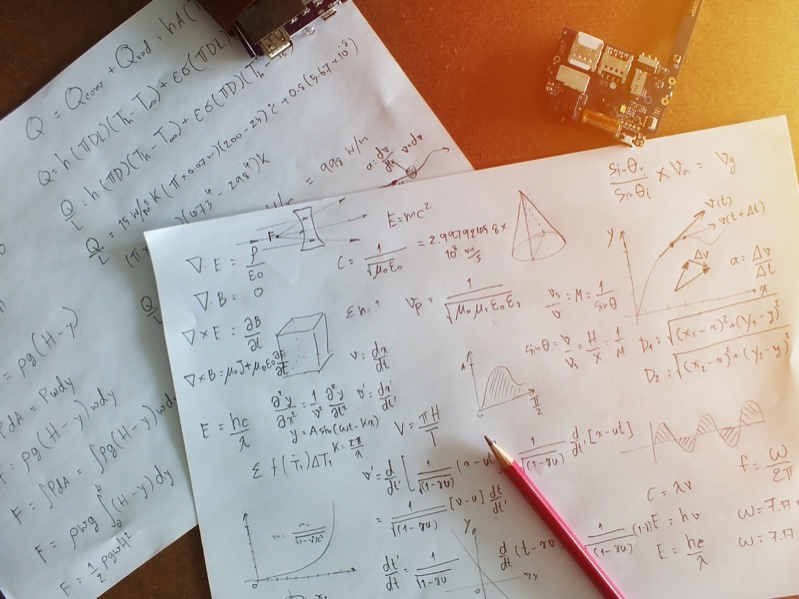
当然ですが、中堅校といえども中学受験をして合格しなければ入学できません。
そのためにはきちんと受験勉強をしなければならず、これは中堅校でも例外ではないのです。
確かに最難関校・難関校などと比べれば入試問題は易しいかもしれませんが、それでもきちんとした対策なしに突破できるものではありません。
以下、中堅校に合格するためにやるべきこと・勉強ポイントなどを整理していきます。
傾向ごとの対策は徹底しなくてはならない
そもそも中学受験というのは、学校によって様々な傾向があります。
例えば選択肢問題・記号問題が多い学校もあれば、記述式の問題が多い学校もあり、選択肢問題・記述問題も含めて幅広い設問形式が出題される学校もあります。
そのあたりは各校で傾向が変わりますので、まずは過去問を通じて傾向を確認し、どのような対策を進めるべきかチェックしなくてはなりません。
もちろん基本は正確におさえることが大前提です!
もちろん、傾向ごとの対策の前提として、各科目の基本は正確におさえておく必要があります。
いくら出題傾向に沿った対策を進めたとしても、各分野・各単元の基本が正確でなければ実力はなかなか伸びません。
正確な計算力や論理的な思考力が身についているか、読解力は身についているか、社会・理科の基本知識を幅広く身につけているかなど、各科目の基本を正確にしたうえで、それぞれの傾向に沿って対策を行うことが大事です。
多様な設問形式に注意しなくてはならない
先ほど述べたように、中堅校は独自の教育方針や校風を打ち出すケースが多いです。
その独自性が入試問題に見られる場合もあり、設問形式がかなり特殊なケースもあります。
例えば記述問題の中でも、論述に近い問題が出されたり、深い考察が求められる問題が出されたりなど、単なる記述問題にとどまらない設問も一部見られます。
もちろん難関校でもこうしたハイレベルな記述問題は見られますが、近年は中堅校でも様々な記述問題が増えているので注意しなくてはなりません。
また、算数でも、ただ単に解答だけを書かせるのではなく、その途中式や考え方、解法手順を記述させる問題も見られます。
中堅校でもこうした設問が含まれることに注意しなくてはならず、ただ単にオーソドックスな設問形式に慣れておけば良いわけではないのです。
そのほか、他の学校では見られないような特殊な形式の問題・設問がある場合など、過去問から出題傾向をしっかり把握する必要があります。
論理的な思考力を身につけるためには?
近年の中学受験では、論理的な思考力を特に重視する傾向が強いです。
これは中堅校も例外ではなく、単なる知識の暗記だけで対応できるわけではありません。
この点は特に注意し、日頃から思考力を鍛えることを意識する必要があります。
4教科それぞれに必要となる思考力と具体例
論理的な思考力というのは、物事を順序立てて考えていく力になります。
「なぜそうなるのか?」を考え、一つひとつ物事を順序立てて整理していくわけです。
そして、このような論理的思考力は、算数・国語・社会・理科のあらゆる場面で必要になります。
以下、具体例も踏まえて整理していきます。
算数
そもそも算数というのは、ただ単に計算を進めれば良いわけではありません。
例えば文章題であれば、長い文章から設問の意図を読み取り、与えられた情報・条件を整理し、解答を導く必要があるのです。
このように、与えられた情報・条件をもとに「問題を解決するにはどうするか?」を考えるのは、まさに物事を順序立てて考えていく思考力に他なりません。
また、複雑な計算処理・作業が必要な設問などでも、思考を深めながら解き進める問題は多いです。
このような問題はワンパターンの解法に沿って解くわけではなく、一つひとつの計算処理や作業をコツコツ進め、「なぜそうなるのか?」を考えながら解かなくてはなりません。
特に何パターンか解法があるような問題では、それぞれの場合で計算処理・作業がどう進むのか?を考えるとより思考が深まるでしょう。
このように、算数というのは単なる計算ではなく、あらゆる場面で思考を深めながら解き進めるケースが多いです。
日頃の問題演習ではこのような点を特に意識し、「なぜそうなるのか?」という思考や解法手順を意識してみてください。
ただ問題を解いて終わりではなく、
「なぜそうなるのか?」「なぜこの解法を使ったのか?」「どのような手順で解答が導き出されたのか?」など、
順序立てて整理していくと、思考力を鍛えるトレーニングになります。
国語
国語の読解力も、物事を順序立てて考えていく力に含まれるでしょう。
文章を読み、その内容を順序立てて整理し、文章が伝えたい内容を理解していくのは、論理的な思考力とも深く関係するわけです。
特に読解力は社会に出ても非常に重要なスキルであり、論理的な思考力をもって文章を正確に読む力はあらゆる場面で必要不可欠です。
そして、最近の中堅校では単なる学問にとどまらず、社会に出て必要なスキルを重視する学校も多いため、そのような教育方針が入試問題に大きく反映される可能性もあります。
繰り返しますが、論理的な思考力・読解力が必要なのは難関校だけではありません。
いずれの中学校でも、国語では読解力と思考力がより重視されるため、物事を順序立てて整理しながら理解を深めていくトレーニングが大事です。
読解問題を解く際には、しっかり解答の解説も確認し、自分の読解が間違っていないかどうか、自分が考えた論理展開が正しかったかどうか、細かくチェックしてみましょう。
社会・理科
社会や理科は暗記科目というイメージが強いですが、社会も理科も単なる暗記だけで対応できる科目ではありません。
特に理科に関しては「なぜそうなるのか?」という思考が非常に重要であり、実験・観察問題などでも高度な思考力が要求されます。
また、社会もただ知識を暗記するだけでなく、歴史の時代背景など、「なぜその出来事が起こったのか?」という点まで思考することが重要です。
さらに、中学受験では各大問のリード文が長い傾向があり、設問を解くにはそのリード文をまず正確に理解しなければなりません。
これは各分野の知識に加えて読解力や思考力が必要であり、単なる知識の暗記で対応できるものではないのです。
また、社会も理科も問題の中に様々な資料が登場するため、各資料の内容を正確に読み取る情報処理能力も求められます。
そして、この情報処理能力も、物事を順序立てて整理する思考力と深く関係しており、中堅校の受験においても非常に重要なスキルになります。
このように、社会と理科は単なる暗記科目ではないという点をまず意識しなくてはなりません。
そのうえで、何か知識を整理するときに、「なぜそうなるのか?」という点まで考える癖をつけましょう。
歴史の時代背景を考えたりなど、ちょっとしたことでも「なぜそうなるのか?」と意識してみる習慣が大事です。
中堅校合格のために必要な勉強量はどのくらい?

繰り返しますが、中堅校といってもきちんとした受験勉強と準備は必要であり、ある程度長い期間でコツコツ受験勉強を重ねる必要があります。
勉強量に関しては各ご家庭やお子さんの状況で変わるため一概には言えませんが、以下、ポイントを整理していきます。
いつから受験勉強をスタートすべき?
中学受験の受験勉強は、一般的には小学校高学年からスタートすることが多いでしょう。
特に難関校を受験するのであれば4年生からみっちり勉強することが多いですが、中堅校を受験する場合で4年生のうちから勉強をスタートするケースも少なくありません。
ただ、最難関校・難関校を受験するケースと異なり、必ずしも受験勉強一筋とまでは言えないでしょう。
上位校を受験する場合、受験勉強を最優先するスケジュールになるかと思いますが、中堅校を受験する場合であれば、そこまで勉強最優先という雰囲気ではないかもしれません。
受験勉強を開始する時期も、必ずしも4年生からみっちり学習を進めていくわけではなく、5年生以降から勉強をスタートするケースも見られます。
もちろん、6年生やラストスパートの時期など、受験勉強が中心の生活になることはありますが、全体を通じてそこまで受験勉強一筋の生活リズムとは言い切れず、ここが最難関校・難関校を受験するケースとの違いと言えます。
家庭学習の勉強時間
家庭学習の勉強時間は各ご家庭やお子さんの学習状況によって大きく変わりますが、意識していただきたいのは「長時間勉強すれば良いわけではない」という点です。
勉強は集中して行ってこそ効果が発揮されるのであり、単に机に長時間向かえば良いわけではないのです。
むしろ、やみくもに長時間勉強させるだけだとお子さんの勉強嫌いを引き起こす原因にもなり、これでは受験勉強の意義が薄れてしまいます。
あくまで勉強は集中して行うことが基本であり、勉強時間が多ければ良いわけではないという点を意識する必要があります。
学年別!家庭学習の勉強時間の目安
4年生・5年生
まず4年生と5年生の家庭学習についてです。
あくまで目安ですが、一日の家庭学習時間は4年生で1~2時間程度、5年生で1~3時間程度になるかと思います。
休日であれば勉強時間が増えると思いますが、平日かつ通塾日の場合は1時間、あるいはもっと少なくなるかもしれません。
このように、通塾日かそうでないか、平日か休日かで家庭学習は大きく変わりますが、いずれの場合も無理のない範囲でコツコツ勉強を進めていくことが大事です。
6年生
6年生になると通塾ペースが増えるほか、塾の授業量も増えます。
そのため、平日で通塾日であれば、そもそも帰宅時間が遅い場合も多く、家庭学習時間はあまり確保できないかもしれません。
ただ、こうした平日かつ通塾日の場合でも、その日のうちに復習をしたいときなど、できれば30分~1時間程度家庭学習時間を設けておくと効果的です。
一方、平日で通塾日でないときは、3時間程度は家庭学習を行うと良いでしょう。
さらに、休日の場合は時間的な余裕も増えますし、通塾日でないなら8~10時間程度家庭学習で勉強することも可能でしょう。
このように、6年生は4年生・5年生より何かと忙しくなり、勉強量・勉強時間も増えます。
ただし、いずれの場合でも休憩時間はしっかり確保し、集中力を維持することが大切です。
繰り返しますが、ただ単に長時間机に向かっても集中できるわけではありません。
たとえトータルの勉強時間が8~10時間程度だとしても、休憩は適宜確保し、その都度頭を休め、集中力を維持する必要があるのです。
まとめ
今回は、中学受験で中堅校に合格するために意識すべきことについてお話ししていきました。
中堅校とはいっても、しっかり受験勉強に取り組んで基礎を磨き、各校の傾向に沿った対策を進めることは大前提になります。
中堅校というと入試問題が易しいというイメージを抱く方も多いですが、あくまで最難関校・難関校に比べれば比較的易しいというだけであり、きちんとした受験対策は必要不可欠です。
特に近年の中学受験では思考力を重視する傾向が強まり、中堅校も例外ではなく、暗記だけで対応できるわけではありません。
各科目の基本を正確に理解することは大前提ですが、そこに加えて論理的な思考力を磨くことを日々心がけ、少しずつ実力を鍛えていく必要があります。
また、独自の設問形式が出題されることもありますので、各校の傾向は細かく確認し、対策の方向性をしっかり定めなくてはなりません。
一方で、ただ長時間勉強を進めれば実力が伸びるわけではなく、あくまで無理のない範囲で学習を進めることが大事です。
また、中堅校を受験する場合、最難関校を目指すようなハードスケジュールとは異なりますし、ただ単に多くの勉強量・勉強時間を確保すれば良いわけではありません。
各校の難易度や傾向を確認し、各ご家庭の教育方針やお子さんの学習状況なども踏まえ、適切な勉強量・勉強時間を意識することが大事です。
こうした点も注意し、目標に向かって有意義な受験勉強を進めていきましょう。