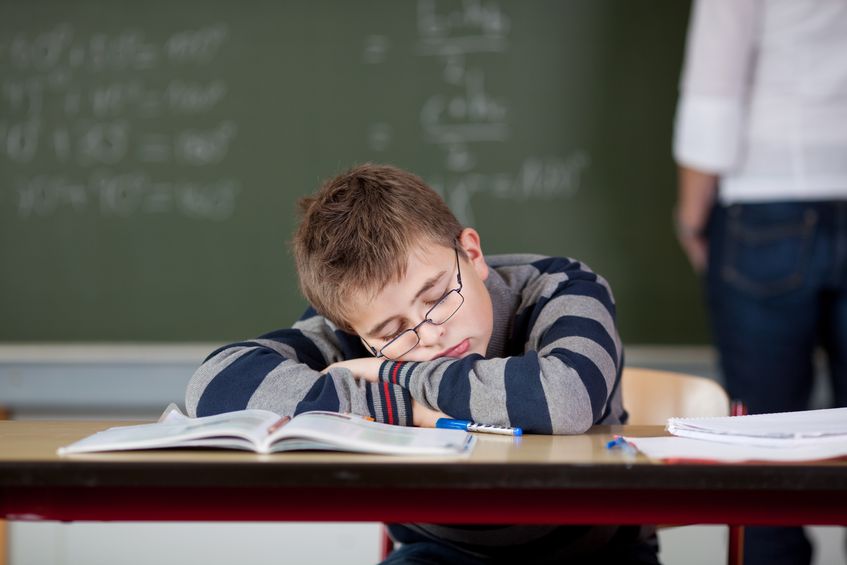付属校に入って大学までエスカレーターで進学するのか、それとも大学受験を経て大学に進学するのか、悩みどころになるでしょう。
この記事では、付属校のメリット・デメリットも踏まえ、付属校から大学に入るべきか、それとも大学受験をするべきかについて、塾講師の経験からポイントをご紹介していきます。
志望校を決める際の参考にしてみてください。
目次
中学受験、その先の大学進学の方法を考えていますか?
大学の付属中学の受験を考えているご家庭も多いでしょう。
付属校は、中学受験さえ乗り切れば大学までエスカレーターで進学できるところに大きな魅力があります。
一方、付属校といっても、大学への内部進学状況は学校によって異なります。
また、付属校にいながらも結局外部の大学に進学したというケースも、実は多いのです。
中学受験をする際にはこうした事情も踏まえ、中学受験のその先、つまり大学進学の方法まで考慮することが大切です。
そして、付属校から大学に進学するのか、それとも大学受験をするのかを考えるには、まず付属校のメリット・デメリットを把握したうえで判断する必要があります。
以下、付属校が持つ主なメリット・デメリットから整理していきましょう。
付属校を志望するメリット

大学へ進学できる安心感
付属校の大きなメリットは、やはり大学への進学が保証されているという点でしょう。
よほどのことがない限りエスカレーターで大学まで進学できるのは、子どもとしても親としても安心感が大きくなります。
また、付属校から外部の大学に進学したい場合も、内部進学という保険がある状態で受験勉強ができます。
もし大学受験に失敗しても、内部進学すればひとまず大学に行けるわけです。
いずれにせよ、大学へ進学できるという安心感は付属校の大きなメリットとなります。
やりたいことに熱中出来る
付属校で大学に内部進学する場合、受験勉強をする必要がないので、やりたいことに熱中しやすいというメリットがあります。
例えば部活に打ち込んだり、受験勉強以外のやりたい勉強に打ち込んだり、熱中するものの選択肢は広がるでしょう。
もちろん、大学受験をさせる進学校でも部活動が盛んな学校はたくさんあります。
ただ、大学受験をプレッシャーに感じながら部活を続けることになるので、時としてストレスを感じる子どもも見られます。
一方、付属校の場合はこうした大学受験のプレッシャーがないため、思う存分部活などに熱中しやすくなるわけです。
大学と連携した教育が行われる
付属校では、大学の設備をそのまま利用できたり、大学と連携した授業・講義が行われたりするなど、何かと大学と連携した教育を受けやすいです。
もちろん、どの程度大学とつながりが深いかは付属校によって異なりますが、大学の教育環境を活用できる機会は多く見られます。
そのため、受験勉強とは違った形での勉強を多く経験できるのです。
例えば、大学の設備を利用した実験など、一般的な受験勉強では経験できないような授業もあります。
付属校のメリットは内部進学に関することだけでなく、こうした教育環境にも現れています。
付属校を志望する際に考慮しておきたいこと
次に、付属校を志望する上で、考慮しておきたいことをみていきましょう。
希望する学部に進学できるとは限らない
付属校はエスカレーターで大学まで進学できますが、その大学に本当に自分が希望する学部があるとは限りません。
高校生くらいになって行きたい学部が決まったものの、いざ調べたら進学先の大学にその学部がなかった、などのケースもあり得ます。
そうなると、外部大学への受験を考慮せざるを得ないでしょう。
また、希望する学部が進学先に存在するとしても、成績によっては希望学部に入れないこともあるのです。
学部の割り当ては基本的に成績順で決まるので、特に人気の学部であれば必然的にハードルが高くなるわけです。
例えば、成績が原因で法学部に入れず、それでも法学部に行きたいのであれば、外部の大学の法学部を受験するしかありません。
このように、内部進学そのものは可能でも、必ずしも希望通りの学部に進めるとは限りません。
この点はあらかじめ知っておく必要があります。
外部受験をしたら内部進学ができない場合もある
付属校によっては、外部受験をしたら内部進学ができなくなる場合もあります。
外部受験の捉え方は付属校によってさまざまであり、外部受験にオープンな学校もあれば、あくまで内部進学をすべきという方針の学校もあります。
もちろん絶対に外部受験できないということはありませんが、外部受験をしたら内部進学ができなくなるというのは、大学進学として考えると非常にリスクが大きくなります。
内部進学枠を蹴って、万が一外部受験に失敗してしまったら、現役で大学に進学できなくなるからです。
この点については特に注意し、それぞれの学校の方針を事前によく確認しておいてください。
勉強する習慣が減るおそれがある
付属校に入って内部進学をすれば、高校受験も大学受験も必要ありません。
そのため、エスカレーターで進学できるからといって安心し、怠けてしまうおそれがあるのも事実です。
そして、中学・高校で勉強する習慣が減ると、大学に入って苦労するおそれがあります。
大学では難しい内容の文献・資料を読む機会も増えます。
また、英語を活用する機会も多いです。
このような場面では、厳しい大学受験を乗り切った受験生の方が、高い読解力・英語力を持っているという意味で有利です。
こうしたケースに内部進学生が対応するには、中学・高校でしっかり勉強を継続しなければなりません。
さらに、あまりに成績が悪い場合、学校によっては高校・大学への内部進学が難しくなる場合もあるのです。
こうした事態を防ぐためにも、付属校といえどもしっかり勉強をすることは大前提です。
先ほども述べたように、学習環境そのものは付属校でももちろん充実しています。
進学の危機感が少ないことから、確かに勉強する習慣が減るおそれはありますが、勉強できる環境はしっかり整っているので、きちんと有効活用することが大切です。
付属校から進むのか大学受験をするのか判断する6つのポイント!

1.選択肢を増やすために付属校に入っておくという考え方
付属校の場合、内部進学だけでなく、外部の大学に入るという選択肢もあります。
外部の大学に絶対入れないという仕組みはないので、内部進学か外部進学かの二つの選択肢があるわけです。
一方、付属校でない中高一貫校の場合、受験や推薦などで大学に入るしかありません。
必然的に外部進学という選択肢しかないのです。
つまり、単純に考えると付属校の方が選択肢は多くなります。
先ほども述べたように、内部進学できるという保険は、やはり心強いものになるでしょう。
そのため、選択肢を増やすために付属校に入っておくという考え方も重要な意味を持ちます。
付属校に入り、ひとまず内部進学を考えておき、途中で志望が変わったら外部の大学の受験も検討する、という形で柔軟に考えることが可能です。
2.付属校で受験勉強をする際の注意点
付属校でも外部進学という選択肢はありますが、付属校で受験勉強をするときにはいくつか注意点があります。
まず、付属校の場合は大学受験にそこまで力を入れていないケースも多いです。
そのため、外部進学を考えるなら、自分で受験の情報を集めて自分で判断すべき部分が多くなります。
また、周りの大半が内部進学をする中で受験勉強をすることになれば、時に心細さを感じることもあるでしょう。
このような状態もある程度覚悟したうえで、受験勉強を行う必要があります。
付属校で受験勉強をしながら、あまりに肩身が狭い思いをしてしまえば、最悪の場合、外部受験を諦めることにもなりかねません。
そうなると、むしろ付属校以外の中高一貫校の方が、柔軟に進学先を選べるという点で選択肢が広がる、という話になってしまいます。
さらに、先ほども述べたように、学校によっては外部受験をしたら内部進学ができなくなる場合もあります。
この点には特に注意しなくてはなりません。
3.付属校でも外部進学の情報をチェックしておく
内部進学も含めて進学先を決められるという点では、確かに付属校の方が選択肢は多くなります。
ただ、付属校での受験勉強が大きな負担となり、内部進学せざるを得なくなれば、結局は進学先の選択肢は狭まってしまうのです。
そのため、外部進学も視野に入れつつ付属校を希望する場合は、その付属校が外部受験にも力を入れているか、外部の大学にも進学しやすい雰囲気か、外部の大学への進学実績があるか、事前によく確認することが大切です。
ホームページ、オープンキャンパス、学校説明会など、さまざまな機会を活用して情報を集めておきましょう。
4.最初から大学受験をさせたいと考える場合
子どもには経験として大学受験をさせたい、と考えるご家庭も多いでしょう。
大学受験をさせることが前提の場合、付属校以外の中学校から優先的に志望校を決める形になります。
先ほども述べたように、付属校は内部進学が可能のため、進学の危機感はどうしても少なく、勉強の習慣が減るおそれがあります。
そのため、緊張感を持って受験勉強をする環境とは言えない場合もあるわけです。
もちろん付属校によって環境・雰囲気は異なりますが、緊張感のある受験勉強によって難関大学を目指したい場合は、大学受験の実績が高い中学校を志望するべきでしょう。
ただ、こうした場合でも、併願校として付属校を受験するという選択肢もあります。
先ほども述べたように、付属校でも外部受験そのものはできるので、付属校を併願校にしても損をすることはありません。
5.最終的には子どもの意思を尊重すること
中学受験では、子どもだけで志望校を判断することは確かに難しいです。
受験だけでなく、その先の大学への進学をどうするか、付属校にするかそうでないかなど、諸々の点を考慮しなければならないからです。
一方で、中学受験というのは、あくまで子どもが「この学校に行ってみたい」「この学校でこういうことがしたい」といった希望を持っていることが大前提です。
親が子どもの意思を無視して受験させるものではありません。
そのため、子どもが付属校を希望している場合、あるいは子どもが気に入った学校がたまたま付属校だった場合、まずは子どもの意思を優先してあげてください。
同じように、子どもが付属校以外を希望する場合、あるいは子どもが行きたがっている学校がたまたま付属校ではなかった場合も、子どもの意思を優先してあげるべきでしょう。
そのうえで、付属校にするかそうでないか、付属校から大学に入るべきか、それとも大学受験をさせるべきか、など、親の意見・見方を子どもに伝えることが大切です。
6.まずは中学高校の過ごし方を考えましょう
中学受験で大学進学の在り方(付属校から進むのか大学受験をするのか)を考えることはもちろん大切です。
ただ、上記でも述べたように、中学受験は「この学校に行ってみたい」「この学校でこういうことがしたい」といった子どもの希望を尊重することが何より大切です。
そのため、子どもが中学高校6年間で本当に楽しく過ごせるのか、充実した6年間を過ごせるのか、きちんと考えなくてはなりません。
そのうえで、大学進学の在り方を考慮することになります。
いくら大学進学に有利な学校(付属校かどうかを問わず)に行っても、その6年間が子どもにとって負担になるようなら、中学受験として成功したとは言えません。
大学進学のことを考慮することも大切ですが、まずは中学高校の過ごし方を考え、受験する中学校が本当に子どもに合っているかどうか、十分に検討することが大切です。
まとめ
今回は中学受験のその先の話として、付属校から大学に入るべきか、それとも大学受験をするべきかについて、判断のポイントをご紹介しました。
付属校にするかどうかは難しい問題であり、大学進学に対する捉え方も、ご家庭によってさまざまです。
こうしたメリット・デメリットを把握し、付属校にするかどうか検討する必要があります。
そして、何より子どもの意志を尊重しなくてはなりません。
中学受験のその先を考えることは、子どもだけでは確かに困難です。
ただ、中学受験は、子どもが「この学校に行ってみたい」「この学校でこういうことがしたい」という気持ちを個人差はあると思いますが、持っているはずです。
そのことを忘れず、親として中学受験のその先の話もしつつ、子どもの意思を大切に、総合的に検討してみてください。