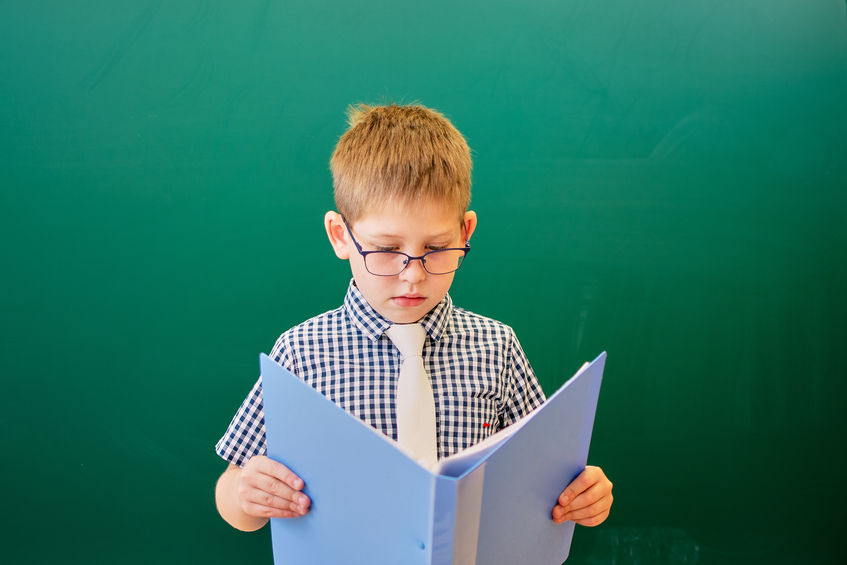無事に卒園式を迎えることができるのだろうか、小学校に入学する前に何を身に付ければいいのだろう…と、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
卒園式直前に慌てないよう、身につけておきたいことを事前に把握しておくといいですね。
ここでは、元幼稚園教諭の経験から卒園前に身に付けておきたいことや、家庭でもできる準備や心構えを紹介していきます。
卒園や小学校入学に不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
幼稚園・保育園と小学校の生活の違いとは?
幼稚園・保育園と小学校の大きな違いは活動内容です。
今までは遊びが中心だった活動が、勉強中心に大きく変化します。
その活動内容の変化に伴い、子どもたちの生活を取り巻く時間の感覚も変化します。
今までは、遊びや工作、歌などの活動とトイレ、食事などが大枠の時間の中で区切られていたのに対し、小学校では1授業45分の区切りで生活していくようになります。
活動内容、一日のスケジュールが大幅に変わることで、初めは戸惑いを感じる子も多いようです。
少しでも、子どもの不安や戸惑いを減らすためにも、卒園までに新生活に向けた準備を少しずつ進めていく必要があります。
卒園に向けて身に付けたい5つのこと

小学校での新たな生活を意識しながら、年長組の子どもが卒園までに身に付けたい5つのことをお伝えしていきます。
園によって指導内容や指導方法は異なりますが、家庭でも実践できるポイントを合わせてお伝えしていくので、少しずつ家庭でも実践してみてください!
1.挨拶やお礼を言える
挨拶やお礼は身につけるべき生活習慣の中の基本中の基本。
入園前から挨拶やお礼の習慣はきちんと身に付いているというご家庭も多いと思いますが、挨拶をしない、お礼が言えない子どもたちが増えています。
挨拶をするとき、お礼を言うときに相手を見ずに下を向いている、声が小さくて聞こえないといったこともあります。
元気にあいさつする、相手の目を見てお礼を言う、など基本がしっかりと身についいているか確認しましょう。
また先生や身の回りの大人に対して「おはようございます」「ありがとうございます」など丁寧な言葉遣いも徐々に身につけていくといいですね。
2.いすに座り、落ち着いて先生の話を聞く、活動に参加する
次に身に付けたい習慣は、いすに座り落ち着いて話を聞くこと、活動に参加することです。
幼稚園では、入園後から座って落ち着いて先生の話を聞くことを指導しています。
繰り返し伝えていくことで徐々にできるようになりますが、集中力が続かない子やすぐに動き回ってしまう子もいます。
ご家庭でも、ごはんを食べるときにすぐに席を立つ、親の話を聞いてくれないとお悩みの方も多いはず。
「座りなさい」「話をしっかり聞いて」など、繰り返し同じ注意をしても子どもたちは耳を傾けません。
そんな時は一度、環境や気持ちをリセットしてみましょう。
例えば、遊びに夢中で話を聞かないとき、話をすることは一旦ストップして子どもの欲求が満たされるのを待ちます。
「○○までやって、そしたらママのところにきてくれる?とても大事な話があるからゆっくり話がしたいの」と伝え、子どもの気持ちが満たされ、落ち着いてからもう一度話をすると子どもは集中して話を聞くようになります。
幼稚園の年長クラスで、学習ワークの活動をしたいのにクラス全体が騒がしく集中できない雰囲気のときがありました。
その対処法として、一旦鉛筆を置き、ワークを閉じ、全員で席を立って、思い思いに体を動かし、もう一度席に座って、黙想の時間を設けてから、活動を再開する方法を取りました。
すると、不思議なほどに雰囲気がガラッと変わり、集中してワークに取り組むことができました。
気持ちを切り替えて集中力をアップする方法を繰り返すことで、今後も学校で授業が始まったときに気持ちを切り替えて集中できるようになります。
「聞く力」を育て、集中力を高め、小学校の授業に備えたいですね。
3.鉛筆や箸の正しい持ち方を身につける
鉛筆の持ち方や、お箸の持ち方は幼稚園でも指導していくことですが、ひとりひとりにつきっきりで指導していくことは難しいので細かな部分は家庭でフォローしていく必要があります。
一度間違った持ち方で定着してしまうと、その後に矯正していくことが大変なので、最初は根気強く練習しましょう。
正しい鉛筆の持ち方が徐々に分かってきたら、ひらがなを書くのではなく、直線や曲線など、基本的な線の書き方を練習しておくと、平仮名、カタカナに応用が利いて、きれいな文字を書けるようになります。
一般的な市販の文字練習用ワークも、始めはそのような線のページがあるので、繰り返し書いてみましょう。
箸の練習は、実際の食事中はもちろん、箸の練習用おもちゃを使って遊びの中で楽しく学ぶ環境作りをすることもおすすめです。
4.自分の名前を書く、読む
平仮名の学習や名前の書き方は小学校入学後にも習うことですが、自分の名前の読み書きはマスターしておくと安心です。
自分の靴箱やロッカー、配布物など名前が書かれたものを見て判断できると学校生活で困ることが減ると思います。
小学校に入学すると、幼稚園の頃と比べて生活の中で先生がフォローしてくれる部分が減ります。
自分のことは自分で行い管理することが求められるため、自分の名前の読み書きは、幼稚園でも家庭でも練習を重ねておきましょう。
5.時計の見方を理解する
時計を読む、時間を意識して生活することも卒園までに身に付けたいことです。
時間を意識できるようになると、生活のさまざまなシーンで自発的に動くことができるようになり生活リズムが整うメリットもあります。
すぐに身に付くことではないので、生活の中で徐々に時間を意識させることが大切です。
幼稚園でも、
「時計の短い針が11のところにきたら、何時になるかな?そうだね、11時だね。11時には外遊びはおしまいでお部屋に入ってきてね」
など、子どもたちと時間を確認しながら、時間を意識し行動ができるように声掛けをしています。
手作りのアナログ時計を用意し、実際に子どもたちに見せて目で見てわかるような働きかけもしています。
家庭でも同様に、アナログ時計を使って、
「短い針が8になって、8時になったら幼稚園のお支度始めようね」
など、子どもに時間を意識させつつ、自発的に身の回りのことができるようサポートしていきましょう。
手作りのアナログ時計がなくても、紙やプラスチックで作られた時計が購入できますので、そのような教材を使ってみるのも分かりやすいと思います。
卒園までに少しずつ身につけていきましょう!
年長組になり卒園や小学校入学を考えるようになるとさまざまな悩みや不安が尽きないものです。
今回は5つの習慣をご紹介しましたが、うちの子はあれもできない、これもできないと焦る心配はありません。
親の焦りや心配は言葉に出さなくても子どもに伝わり、卒園が近づくと情緒が不安定になってしまう可能性があります。
少しずつ、子どもに合った指導法を見つけ、卒園までにできる範囲で楽しく身に付けていきましょう。