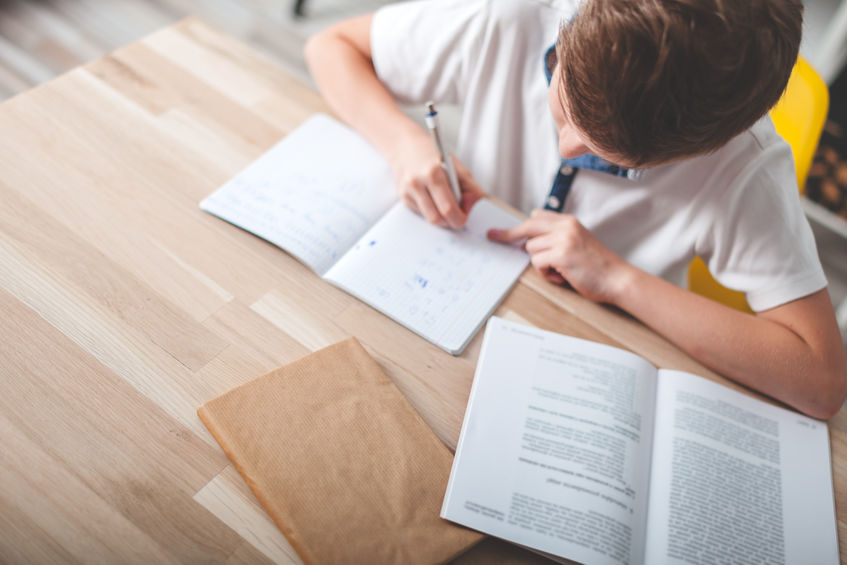目次
子どもの幼児期にしておきたいこと
まっさらな幼児期に、将来子どもにどんなことをさせたいですか?
親御さんは期待を込めて考えているでしょう。
現在、首都圏の公立小学校の約8割は公立中学校へ進学するため、中学受験をする家庭は少ないと言えます。
そんな中、自分の子どもが中学受験をするのに適性かどうかを見極めることが大事になります。
見極める方法としては、幼児期から、幼児教室に通わせてみる、自宅でテキストを買ってそれを使って数の勉強や言葉の知識を学ぶなどの方法があります。
早くからの教育をすることによって、子どもが落ち着いて勉強に向かえる子なのか運動向きの子なのか、わが子の適性を早くから認識できるようになり、将来への期待の方向性もかわっていきます。
小学生からの塾選びは複数検討を
塾と一言で言っても、いろいろな塾があります。
集団や個別、家庭教師など選択に迷います。
子どもの普段の学校の宿題の仕方を見て、集団で他の子供たちと競い合うほうがいいのか、じっくりと先生と個別で教えてもらう方がよいのか、体験期間がある塾がほとんどなので電話で問い合わせ体験をしてみることが重要になります。
それも一校だけではなく、複数体験してみることによって子供との相性がわかります。
中学受験の検討は3年生からでも遅くない!
塾は小学1年生からありますので、週に一度のペースからでも勉強する癖をつけることができるようになります。
受験をするかどうかは小学3年生ぐらいから考えても遅くありません。
受験に必要な試験に出る勉強を具体的に始めるのは小学4年生からなので、それまで自分の子どもが受験に向いているのかどうかを見極めることができます。
塾の定期テストで塾全体の何位の成績なのかはっきりとわかるので、受験しようかどうか迷うときにはいい判断材料となるでしょう。
中学受験を決めたら早めの入塾を!

受験を考えるなら早くから入塾して勉強を始めましょう。
算数や国語など実践的な問題が増えてきます。
受験勉強はどれだけ多くの問題を解いてきたかがカギになります。塾をうまく活用して、学校の授業では習えない受験向きの専門的な勉強をしていきましょう。
学年が上がるごとに、定期テストや塾内の組み分けテストも増えていきます。
そのテスト結果を参考にしてお子さんの不得意分野を早くから克服するように心がけて宿題に取り組むようにすると、塾での成績も上がってくるでしょう。
成績が上がらなければ塾の先生に相談を
もし、なかなか成績が上がらないようであれば、遠慮なく塾の先生に相談してみましょう。
塾の先生は過去の経験をもとにいろいろな知識をお持ちですので勉強の仕方や生活リズムまでアドバイスしてくださいます。
学校見学へは必ず行こう
少しでも気になる中学の学校見学は必ず行っておきましょう。
実際に子どもを一緒に連れて行き、学校を見学することで好みや学校生活の違いなどもはっきりしていき、また中学校の授業体験もできるオープンスクールを実施しているところもあるので、予約制か確認し体験してみてください。
年に一度しかない文化祭にも行ってみて、学校の生徒の様子や特色などを見ることもできます。積極的に足を運ぶことで子どもの意識も高まり、志望校を早めに決めるいい機会にしていきましょう。
いよいよ中学受験の6年生へ
学校が休みに入る間に行われる春季講習などは必ず参加しましょう。
6年生になると模試の機会も増えるため勉強したことがテストで試されます。自分が希望する学校へ合格できそうか、合格確率もわかります。
受験勉強をしてきたことが、模試に反映されますし、多くの受験生の中で試験をすることで本番の試験慣れをすることもできます。志望校選択にも模試の結果が参考になります。
こうした全体での自分の成績を子ども自身が知ることで、勉強がどれぐらい身についているのかがはっきりとわかり、受験さながらの雰囲気を味わうことで意識も高まっていくことでしょう。
受験日が近づいたら
受験が近くなったら、最終的な受験校の入試日程の確認や願書・提出書類の取り寄せが始まります。
学校によっては受験日が一日しかないところもあり、他校と重ならないようにするのかダブル受験するのか、各家庭で相談して決めるとよいでしょう。
最後に
一言で中学受験と言っても、塾に通わせていたらそれで安心というわけではありません。
家族の協力も必要となります。
体力面でサポートするための食事に気を付けるのもその一つです。
また、勉強で疲れているときはリラックスさせてあげる場も考えてあげましょう。
幼児期からの教育で子どもの適性を見極め受験まできたなら、家庭での支え方も身についています。
子どもがのびのびと勉強でき、志望校受験まで家族が一丸となって支えていくには、やはり家族の絆が必要不可欠です。